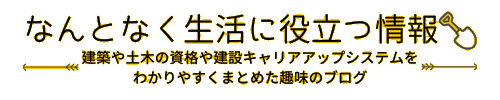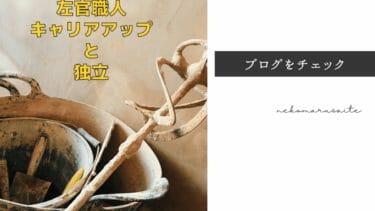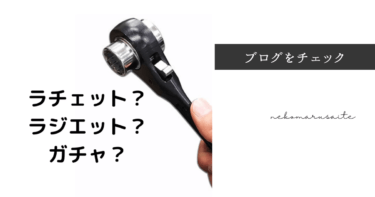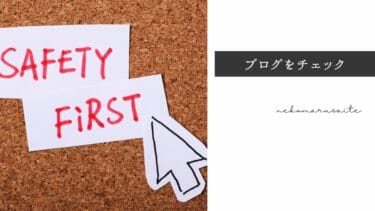この記事では、左官職人さんが使う「鏝(こて)」を選ぶ際に役立つポイントや鏝の種類など、左官職人から土間屋さんが使う鏝に関することを解説していきます。
また、現役現場監督である筆者がおすすめする鏝も合わせて紹介していきたいと思います。
左官工とは、建物の壁や床・土堀などに土やモルタル・漆喰などといった壁材を鏝と呼ぶ工具を使って塗り上げるお仕事をする職人さんです。
そのため、左官職人にとって鏝とは大事な仕事道具であり、日々の仕事を左右する工具でもあります。
最近では、DIVや個人でリノベーションなどで壁材を塗るときに鏝を使う方もいるかと思います。
そんな身近な鏝ですが、その種類は大変豊富にあるため、実は今使っている鏝が違う用途で使うものだったなんてこともあるかもしれません。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。と言う方がいらっしゃいまして建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。
そこで、今回は左官職人さんなら知っておくべき鏝という工具について解説していきたいと思います。
鏝(コテ)とは?
まず、鏝とはどういった工具であるか解説していきます。
鏝とは、以下の通りです。
1.壁土やセメントを塗る道具。多くは鉄製で、平たい板に握り柄をつけたもの
2.和裁で、熱して布地のしわをのばしたり、折り目をつけたりする鉄製の道具。焼きごて
3.頭髪にウエーブをつけるために熱して用いる、はさみ状の整髪具。ヘアアイロン
4.鋳掛けのはんだづけなどに使う、先のとがった金属の棒に柄をつけた道具
引用:Weblo辞書
ここでは、1に説明されている左官工が使う壁面などを塗る鏝「左官鏝」を解説していきたいと思います。
ちなみに、溶接工が使う「焼きごて」、アイロンやヘアアイロンといったものも鏝に含まれるようです。
では、次に左官鏝にはどんな種類があるのか解説していきたいと思います。
その前に左官職人として知っておくべき知識も確認しておきましょう。
「左官職人として現場で働きたいけど求人はあるのかな?」「左官職人は一人親方として独立できるのかな?」など、左官職人に関する雇用に疑問や不安を抱えているのではないでしょうか?そこで今回は、左官職人として働くための基礎知識を分かりやす[…]
左官 コテ 種類:どんなモノがあるの?
左官鏝にはさまざまな種類があります。
レンガ/ブロック鏝(コテ)
レンガ鏝/ブロック鏝とは、壁材を攪拌・すくう・塗る・ならすなどの用途に使われる鏝です。
左官工の作業全般に使われる鏝ではありますが、名前から特にレンガやブロックといったものと積み重ねるときの作業で扱いやすい鏝となっています。
レンガ鏝とブロック鏝の違い
レンガ鏝は、形状が丸く、攪拌・すくう・塗るといった汎用性のある鏝となっています。
そのため、レンガだけでなくブロックを積み上げる際にも使用することができる鏝とされています。現場ではオカメとか言って使ってる職人がいます。
一方、ブロック鏝は先端が細長く平らになっているので、モルタルをブロック縁に塗る、ブロック穴に流し込むといった作業に特化している鏝となります。
形状から、左官工全般で扱うことは難しく、先端が平らで細長いので慣れていないと、モルタルをこぼしてしまう可能性があります。
そのため、ブロック鏝を扱う際は、より専門性を求められる熟練された作業が必要になってくるといえます。特にモルタルをコテ板でこねて、ブロックにモルタルを配っていくブロック職人は見ていて楽しくなります。
外構工事やエクステリア工事では職人は1日でブロック100本積めるぐらいの歩掛で考えてますが、200本積めるとプロですね。
土間鏝(コテ) 土間仕上げ コテ 種類
土間鏝はその名の通り、土間にモルタルを敷く、敷き均し、押さえ均しのときに使う鏝です。
塗る面積が大きく、面積の広い土間での作業を効率よく進めてくれる鏝です。金鏝仕上げと言われる仕上げで土間屋の抑え方で職人の腕がよくわかります。
シゴキ鏝 (コテ)
シゴキ鏝とは、左官工の作業で「しごく(壁材などを擦り付けて塗る方法)」作業をするときに使う鏝です。
他の鏝と違うのは、モルタルなどの薄塗りをしやすくするために、接地面の金属製部分が「しなる」ようになっています。
そのため、他のモルタルに比べて鏝も薄くできているので「シゴキ作業」に特化した鏝といえるでしょう。
モルタル鏝(コテ)
モルタルは、セメントと砂と水を混ぜて作る建築材料です。
セメントの成分の中には、強いアルカリ性が入っているため、モルタルを扱う場合は手袋などをして作業にあたらなければなりません。
当然、このアルカリ性は鏝をも劣化させてしまうので、モルタルを扱う時には耐久性のある鏝を使用します。
そんな作業の時に使われる鏝が。「モルタル鏝」です。
モルタル鏝は、モルタルによる経年劣化がしにくく、鏝の劣化による塗りムラを防いでくれます。
また、鏝の接地部分には金属以外のゴム・合成樹脂・プラスチックといった素材を採用しているので、さびにも強い点があります。
面引鏝(コテ)
コンクリートを打設する際、角にあたる部分はコンクリートが割れやすく、強度が弱くなっています。現場ではピン角とか言われますね。これを面を取る作業で角部分を強化するために角を作る作業のことを「面引」と呼びます。
面引鏝は、この面引の作業に特化した鏝となっているため、角が付けやすいように側面が加工されています。
面引鏝は、その角の形状によって様々な種類があり、面引を行う部分によって鏝を変えながら作業をしていくようになっています。
目地鏝(コテ)
レンガやブロックなどを積み上げたり、敷くときは一度コンクリートをレンガ/ブロック鏝で塗っていくのですが、どうしてもモルタルがはみ出てしまいます。
作業で無駄に出てきたモルタルを削ったり、目地をきれいに仕上げる必要があります。
そうした、レンガやタイルなどの建築物を仕上げるときに使うのが「目地鏝」です。
目地鏝は、接地部分が細長く、他の用途と併用することはできません。
また、目地の幅によって種類は様々なので、目地幅によって鏝を使い分けるようにします。
プラスチック鏝(コテ)
壁材を塗るときや塗装にコテ跡をわざとつけたり、タイルの下地なのでコンクリート打設でタイルの付着をよくするようにザラザラに仕上げをするなど汎用性に優れた鏝となっています。
木鏝に比べて摩耗しにくく、最近では合成樹脂などを使用しているため、耐久性ああり、経年劣化しにくい特徴があります。
中塗鏝(コテ)仕上げコテ おすすめ
モルタルを塗る作業は、「粗塗り」→「中塗り」→「仕上げ塗り」といった大まかな流れで塗っていきます。
この中塗り作業で使われる鏝が、「中塗鏝」です。
中塗鏝は、形状が少し厚くなっていることと、先端がとんがっているものが多いことが特徴です。
左官工の中でも一番使われる鏝なので、鏝といえばこの中塗鏝が挙げられることが多いです。
角鏝(コテ)仕上げコテ おすすめ
角鏝は、仕上げ塗りによく使われる鏝です。
モルタルの押さえこみや、角部分の仕上げにも使われます。
形状は薄いものが多いので、その薄さを利用して「しならせて」扱うこともできる鏝となっています。
ツマミ鏝(コテ)
ツマミ鏝は、指先ほどの大きさしかない小さな鏝です。
主に面引といった細やかな作業に適しています。
クシ鏝(コテ)
クシ鏝とは、主にレンガやタイルといった建築材料を接着するときに使う鏝です。
通常の鏝だと接着剤があまり伸びないので、塗りムラが出てきてしまう可能性があります。
クシ鏝では、凹凸がある形状となっているため、溝に接着剤が均等に入っていくので、塗りムラなく接着剤と塗ることができます。
塗るイメージとしては、工作などで使う糊ベラで糊を塗るような感じで考えると分かりやすいかなと思います。
形状と用途について解説していきましたが、その種類の中でも材質によって更にその用途は細分化されます。
では、次に材質について解説していきます。
その前にこちらの記事も確認おススメの道具箱こちら
職人が使いたい人気の道具箱・工具箱は選ぶのが難しい使いやすい収納箱のまとめ(ミルウォーキー・マキタ・ハイコーキ)
コテの種類は説明してきましたが、次はコテの材質やおススメの商品をまとめていきたいと思います。
- 1
- 2