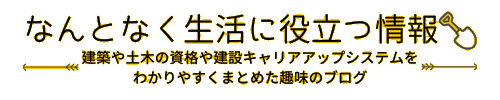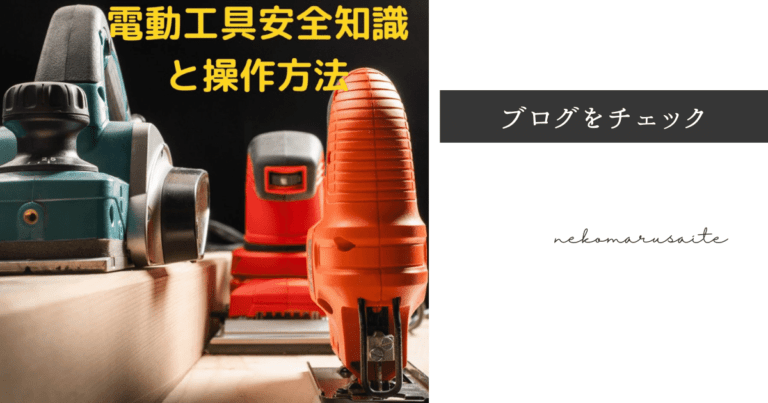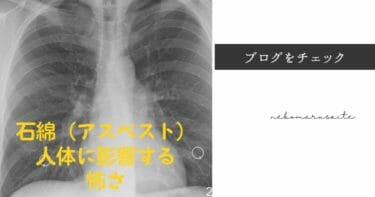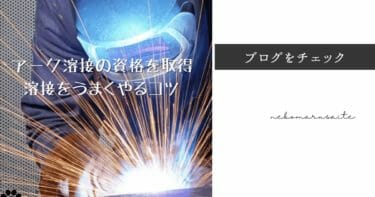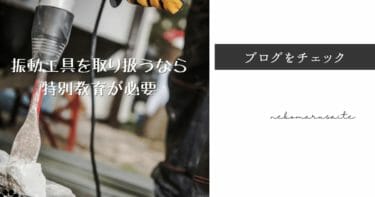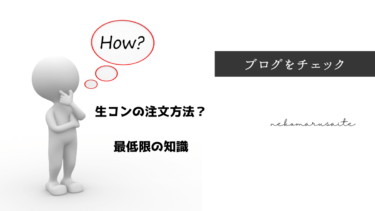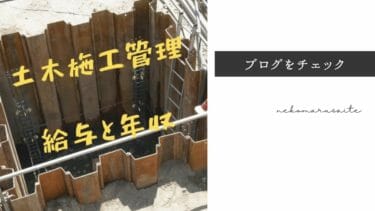この記事では、電動工具の振動、騒音と一番危険な塵肺について、電動工具の取り扱いを解説していきます。
皆さんは、電動工具を取り扱うときは、工具との接触事故でケガをするイメージが強いのではないでしょうか。
ですが、タイトルにあるように電動工具ってケガをするイメージが強いけど、ケガ以外の危険性って何だろう?
と、疑問に感じるのではないかと思います。
そこで、今回は建設現場で日常的に使われている電動工具によるけが以外の危険性とはどのようなものなのか解説していきたいと思います。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。と言う方がいらっしゃいまして
建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。
電動工具は簡単に取り扱いができる工具ですが、様々な危険性がありますので、是非工具を適切に使用するのに必要な知識を一緒に共有していきしょう。
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
電動工具でも起こる塵肺(じん肺)作業とその危険性

怖いのはまずは、これですね
土ぼこりや金属の粒などの粉じんの発生する環境で仕事を行う方が長い年月にわたり、粉じんを多量に吸い込むことで、「じん肺」という病気を引き起こす危険性があります。
現在でも「じん肺」そのものの治療方法はありません。
「じん肺」とは肺の組織が線維化し、硬くなって肺が弾力性を失ってしまう病気のことです。
症状としては、呼吸困難・気管支炎・肺がん・気胸などの合併症を引き起こす可能性もある恐ろしい病気です。
じん肺と同じように怖いのは石綿です。アスベストについての詳しい記事はこちらにあるので合わせて読んでみてください。
この記事では、石綿を取り扱う際の注意すべきことと、安全に解体するための対策を解説していきます。石綿とは、1μm以下の極めて細い繊維の束でできており、1μm=0.001㎜になります。例えば、女性髪の毛が0.08㎜とされている[…]
石綿や解体工事でしか粉じんは出ないだろうと思いがちですが、電動工具においても材料を切削するときなどに粉じんは発生します。
そのため、電動工具を取り扱う場合でも粉じん対策を講じる必要があるのです。
特に、アーク溶接による粉じん被害を重く見た政府は、平成24年4月1日の粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則を改正することとなりました。
アーク溶接は特定化学物質作業主任者専任必要に法律が変わった
粉じんによる恐ろしい病気であるじん肺の危険性を考慮し、屋内に限らず屋外での作業においても以下の措置が必要になりました。
金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」はこれまで「粉じん」として健康障害防止対策が必要とされてきましが、令和3年4月から溶接ヒュームに含まれる化学物質につ いて労働者への健康障害のリスクが高いと認められたことから、粉じん対策に加え、特定化学物質に追加し、ばく露防止措置などの必要な対策をが必要なため、政令と厚生労働省令の改正を行いました。
今年から、特定化学物質等作業主任者の選任や特殊健康診断及び作業環境測定の実施が義務付けられることとなりました。
アーク溶接についての資格や使用方法についてはこちらの記事で解説しているので合わせて読んでみてください。
この記事では、アーク溶接を使用する際の資格を取得する方法と、アーク溶接のやり方などを解説していきたいと思います。アーク溶接って他の溶接と何が違うのだろう?と、このように「溶接」という言葉は皆さん聞いたことがあるので、鉄板や金属を溶[…]
アーク溶接で塵肺にならないためには?
- 呼吸用保護具 (防じんマスク)の使用
- 粉じん作業場以外の場所に、休憩設備の設置
- 常時アーク溶接を行う事業場では、定期的なじん肺健康診断の実施と、じん肺健康管理実施状況報告の提出の義務化
このように、アーク溶接には新たな教育内容が追加されました。
自分の作業する際に設備や保護具がないと塵肺の危険性は高くなります。
※参考:粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改止する省令の施行について
基発0207第1号 平成24年2月7日
アーク溶接作業などで使用する保護具は?
安全備品のユニットは建設業ではモノタロウやアスクルより昔から分厚いカタログで安全備品や危険周知の看板などを販売してくれている、建設業には馴染みのある商社です。
監督がヒマ潰しで見てる人もたくさんいるのではないかと思います。
豊富な建設業関連商品があるので見ているだけでも面白いので、是非合わせてチェックしてみてください。
電動工具など工事現場の騒音対策と身体に与える影響

「騒音が発生する作業」とは騒音が発生する作業のうち、小型機械が関連する作業は以下の通りです。
騒音は、人に不快感を与えたり、会話や連絡、合図などを妨害して安全作業の妨げになるだけでなく、騒音性難聴の原因となることからその防止対策の推進はとても重要です。
- インパクトレンチ等でボルト、 ナット等の締め付け、 取り外し
- 丸ノコ盤で金属を切断
- 岩石や鉱物を動力により破砕し、 粉砕
- さく岩機、コンクリートブレーカー等圧縮空気で駆動する手持
- 動力工具の取り扱い
- チェーンソー、刈払機で立木の伐採、草木の刈払い等
- 丸ノコ盤、帯のこ盤等の木材加工用機械で木材を切断
騒音となる電動工具は上記のようなものが挙げられます。
このように深刻な騒音被害を打開するためにも静音機能がついた電動工具が多数販売されることとなりました。
特に電動工具といえば、「hikoki」と「マキタ」はこのような騒音対策に対して先陣をきっているので是非チェックしておくと良いでしょう。
騒音対策から身体を守る方法
- 施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善されているか作業場所で規定がない場合には注意しなければならない
- 防音保護具の使用や義務化されているか確認
- 騒音作業に常時従事する労働者に対する健康診断の実施(6か月以内ごとに1回)
と、このように作業環境測定を実施し、その測定結果に基づき対策を実施する必要があります。
電動工具による振動作業は身体に大きく負担が掛かる
チェーンソーやグラインダー等による工具機械装置などの振動が主として手腕を通して身体に伝達されることにより発生する被害を振動障害といいます。
振動障害は主に、末梢循環障害・末梢神経障害・運動器(骨·関節系)障害の3障害を指します。
振動障害についての詳しい内容は、こちらの記事に書かれていますので合わせて読んでみてください。
この記事では、電動工具を使用するにも、特別教育を受講しないといけないのか解説していきたいと思います。また、振動工具を取り扱う場合、将来的に病気や後遺症に苦しむ可能性があることと考えた上で、特別教育を受ける必要性も合わせて解説してい[…]
振動工具の該当する電動工具とは

※一部抜粋:「チェーンソー取扱い作業指針」及び「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」より策対
- チェーンソー
- エンジンカッター
- 電動ハンマー等
- 床上用研削盤
- インパクトレンチ
- ジグソー
- さく岩機、コンクリートブレーカー
- コンクリートバイブレーター
振動ばく露による身体への影響を少しでも減らすための努力が必要になります。
その対策の一つとして、振動作業時間を軽減する方法が定められています。
振動作業で1日作業時間は?
振動作業の身体的負担を減らすために1日の作業時間を定める計算方法があります。
つまり、振動工具を使って作業する場所の時間は、計算によって算出します。
まず、日振動ばく露量から算出します。
日振動ばく露量A(8)が、「日振動ばく露限界値」である5.0m/s2を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行います。
ただし、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合でも、「日振動ばく露対策値」である2.5m/s2を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等に努める必要があります。
日振動ばく露限界値(A(8):5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間が、2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とします。
このような計算から算出された時間をもとに振動作業を軽減するのです。
振動工具の3軸合成値及び1日当たりの振動ばく露時間から計算される1日あたりの振動ばく露量について
3軸合成値とは、
手腕にどれだけの振動が伝わるかを推し量るための基になる数値で、発生している振動をX/Y/Z の3方向(3軸)の成分に分けて測定し、周波数別に手腕に伝わる係数を乗じた値(実効値)を合成したもの
「三軸合成値について」:エクセンサポート
と、なります。
ですが、工具ごとに違う三軸合成値をいちいち調べるのは、正直とても面倒なことです。
そこで、一目で振動ばく露量が分かる表があるので是非参考にしてみてください。
電動工具を誤った方法がないように取り扱う知識を知っておくといいですね。工具別に点検の重要性を次にまとめていきたいと思いますので確認してみてくださいね
- 1
- 2