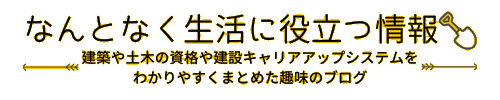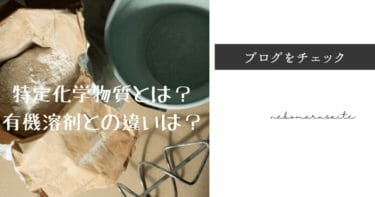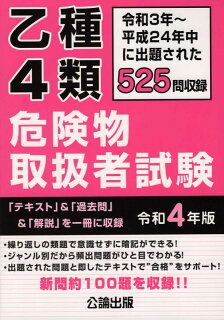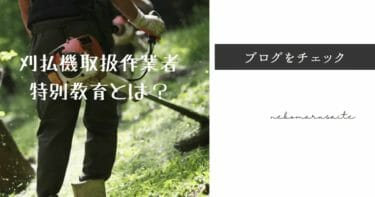この記事では、危険物取扱者という資格はどういうものなのか、また資格を取得する方法を解説していきます。
建築業や製造業など危険物を取り扱うお仕事に関わる方は、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
名前からして危険物を取り扱うことができる人だと思いますが、どの危険物を取り扱えるのか、などよくわからないことが多くある資格ではないかと思います。
今回はそのあたりについても記載させてもらいます。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。
建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。
危険物取扱者とは?資格取得方法と試験内容

危険物取扱者とは、冒頭で解説したようにまさに「危険物」を取り扱うことができる資格のことを指します。
ですが、資格を取得してしまえば危険物全般を扱えると思いがちではないでしょうか。
実は、「危険物取扱者」という資格は3つあり、それぞれ扱える危険物が違うのです。
資格を取得してしまえば、自由に扱えるというわけではないんですね。
危険物取扱者の資格は3つに分けられる
まず、危険物を取り扱うのに必要な資格が3つあります。
それぞれ、
| 区分 | 甲種(こうしゅ) |
| 乙種(おつしゅ) | |
| 丙種(へいしゅ) | |
と3種類に資格が分かれています。
この違いは、取り扱うことができる危険物の種類と受験資格によって分かれています。
危険物取扱者の種類と取り扱い可能な危険物

では、それぞれの種類に分かれて解説していきます。
| 甲種 | 全種類の危険物を取り扱うことができます。 | ||
| 乙種1類 | 酸化性固体塩素酸塩類 過塩素酸塩類 無機過酸化物 亜塩素酸塩類 臭素酸塩類 硝酸塩類 よう素酸塩類 過マンガン酸塩類 重クロム酸塩類 など | ||
| 乙種2類 | 可燃性固体硫化りん 赤りん 硫黄 鉄粉 金属粉 マグネシウム 引火性固体 など | ||
| 乙種3類 | 自然発火性および禁水性物質カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム アルキルリチウム 黄りん など | ||
| 乙種4類 | 引火性液体ガソリン アルコール類 灯油 軽油 重油 動植物油類 など | ||
| 乙種5類 | 自己反応性物質有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 アゾ化合物 ヒドロキシルアミン | ||
| 乙種6類 | 酸化性液体過塩素酸過酸化水素 硝酸 ハロゲン間化合物 など | ||
| 丙種 | 乙種第4類の一部 ガソリン 灯油 軽油 重油 など | ||
このようにそれぞれの資格で取り扱うことができる危険物が違うということが分かります。
危険物取扱者になると?
危険物の取り扱いを、危険物取扱者(甲種、乙種、丙種)が行うことができます。
もしくは危険物の取り扱いをする場合は、危険物取扱者(甲種、乙種)の立会いのもとに危険物取扱者以外の者が行うことができます。
つまり、立ち会って危険物を取り扱うときは、丙種の資格を持つ方ではできないということです。
| 甲種 | 危険物取扱の立ち合いが出来る | ||
| 乙種1類 | 危険物取扱の立ち合いが出来る | ||
| 乙種2類 | 危険物取扱の立ち合いが出来る | ||
| 乙種3類 | 危険物取扱の立ち合いが出来る | ||
| 乙種4類 | 危険物取扱の立ち合いが出来る | ||
| 乙種5類 | 危険物取扱の立ち合いが出来る | ||
| 乙種6類 | 危険物取扱の立ち合いが出来る | ||
| 丙種 | 危険物取扱の立ち合いが出来ない | ||
危険物取扱者になるメリット

危険物取扱者になるとこのようなメリットを得ることができます。
①資格手当がもらえる
企業の就業規則によって資格手当の有無や相場などそれぞれ違いますが、危険物取扱者資格は「国家資格」に分類されるので資格手当をもらうことができます。
資格手当は毎月もらうことができる手当となります。
就業規則によっては、合格したときにもらえる「合格報奨金」もあります。
②就職の幅が広がる
危険物を取り扱うことができるのは、資格を持っている人でしかできない仕事が多くあります。
特に甲種の危険物取扱者になるとすべての危険物を取り扱うことができるので、実務経験なしでも危険物を取り扱うことができます。
また、待遇面も良くなるので企業によっては追加報酬を出しているところもあります。
危険物取扱者の資格を持っていると、その資格を持っている人でしかできない仕事もあるので、是非受験しておくとよいかと思います。
③国家資格だけど比較的取得しやすい
「国家資格」と訊くと、難しいイメージを持つかもしれませんが、国家資格のなかでは比較的取得しやすいというメリットがあります。
甲種は難しいと言われていますが、乙4種は比較的取得しやすい種類ではないかと思いますので、まずはここからチャレンジしても良いのではないかと思います。
資格取得したらやはり単価と給与はベースアップしたいところです。私も実際3回も転職してます。
ただ、なかなか転職サイトをみても建設業に特化した求人が少ないですよ。
そこで、建設業に特化した正社員求人が満載のこちらのサイトを紹介します。登録しておくと、職人や施工管理などの職種から求人を検索できるのであなたの希望する求人を見つけやすくなります。
新しい仕事をこちらで登録してチェックしてみましょう。
危険物取扱を取得するメリットを説明しましたが、ではこの試験の受験概要をこの次にまとめていきたいと思います。
危険物取扱者になるには?ー試験概要ー
危険物取扱者の資格を取得するには、危険物取扱者試験を受験することで取得することができます。
各都道府県の消防試験センターで願書出願・受験をすることができます。
受験資格
甲種
甲種の受験には一定の資格が必要です。
受験資格は、いずれかの条件を満たしている者に限ります。
- 大学等において化学に関する学科等を修めて卒業
- 大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
- 乙種危険物取扱者免状の交付後、危険物取扱いの実務経験が2年以上の者
- 次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者
- 第1類又は第6類
- 第2類又は第4類
- 第3類
- 第5類
- 修士、博士の学位を有する者(化学に関する事項を専攻) ※証明書が必要です。
乙種、丙種
だれでも受験することができます。
| 甲種 | 大学等において化学に関する学科等を修めて卒業 大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者 乙種危険物取扱者免状の交付後、危険物取扱いの実務経験が2年以上の者 次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者 第1類又は第6類 第2類又は第4類 第3類 第5類 修士、博士の学位を有する者(化学に関する事項を専攻) ※証明書が必要です。 | ||
| 乙種1類 | だれでも受験することができます。 | ||
| 乙種2類 | だれでも受験することができます。 | ||
| 乙種3類 | だれでも受験することができます。 | ||
| 乙種4類 | だれでも受験することができます。 | ||
| 乙種5類 | だれでも受験することができます。 | ||
| 乙種6類 | だれでも受験することができます。 | ||
| 丙種 | だれでも受験することができます。 | ||
試験方法
取得する資格と所持している免許、業務経験で試験内容が異なります。
試験はマーク・カードを使う筆記試験になります。
| 種類 | 形式 | 問題数 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 甲種 | 五肢択一 | 45問 | 150分 |
| 乙種 | 五肢択一 | 35問 | 120分 |
| 丙種 | 四肢択一 | 25問 | 75分 |
合格基準は各試験科目ごとの成績が、それぞれ60%以上で合格となります。
試験内容
| 種類 | 試験科目 | 問題数 |
|---|---|---|
| 甲種 | ・危険物に関する法令 ・物理学及び化学 ・危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 15問 10問 20問 |
| 乙種 | ・危険物に関する法令基礎的な物理学及び ・基礎的な化学 ・危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 15問 10問 10問 |
| 丙種 | ・危険物に関する法令 ・燃焼及び消火に関する基礎知識 ・危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10問 5問 10問 |
一部試験科目の免除
危険物取扱者乙種試験科目の免除
| 免除条件 | 免除種類 | 問題数 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 乙種危険物取扱者免状を有する者 | 全類の一部が免除 | 10問 | 35分 |
| 火薬類免状を有する者 | 1類と5類の一部が免除 | 24問 | 90分 |
| 乙種危険物取扱者免状を有し、 かつ火薬類免状を有する科目免除申請者 | 1類と5類の一部が免除 | 5問 | 35分 |
| 消防学校の教育訓練のうち基礎教育又は専科教育の警防科を修了し、 5年以上消防団員として勤務した者 ※証明書が必要です | 一部が免除 | 20問 | 60分 |
危険物取扱者丙種試験科目の免除
| 免除条件 | 免除種類 | 問題数 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 消防学校の教育訓練のうち基礎教育又は専科教育の警防科を修了し、 5年以上消防団員として勤務した者 | ・危険物に関する法令 ・危険物の性質並びに その火災予防及び消火の方法 | 10問 10問 | 60分 |
有機溶剤とか特化物の技能講習などを取得すると仕事の幅は広がりますね。
特定化学物質とは?有機溶剤との違いは?扱うときに必要な資格と技能講習の違いをまとめ講習の内容も解説!
この記事では、特定化学物質を扱う際の資格と資格講習の内容について解説していきます。また、間違えやすい「特定化学物質」と「有機溶剤」の違いについてもあわせて解説していきます。特定化学物質を扱うときは、特化物講習と言われる資格[…]
危険物取扱者の資格を取得するなら通信講座がおすすめ!
危険物取扱者試験の勉強をするのは、どうしても普段の仕事と両立してやらなければいけません。
「仕事と両立して…スケジュール管理して勉強しないといけない」などと考えながら計画して勉強を進めなければいけません。
また、独学だけでは分からないことなど出てきても聞いたりすることができません。
そうしたときにおすすめなのが通信講座を利用してみることをおすすめします。
今回はおすすめの通信講座とテキストを紹介していきますので、是非参考にしてみてください。
技術系の通信講座・資格取得対策の通信講座なら職業訓練法人JTEX(ジェイテックス)
こちらの講座は甲種も取得することができます。
経団連主導の職業訓練法人の通信講座なので信頼と40年以上実績があります。
段階ごとにレポートがあり、その都度赤ペン先生が採点してくれるので自分の力量を推し量ることができます。
オリジナルテキストを元に進めていくので、効率よく勉強を進めることができます。
第1線で活躍する講師陣の生の指導を受けられることも良い点ではないかと思います。
こちらは、テキストになります。
豊富な演習問題でひたすら問題を解くことができ、重要な点に絞って勉強を進めることができます。
また、赤シートがついているので通勤中や空いた時間にも効率よく勉強をすることができます。
効率よく、ババッとポイントを押さえて勉強をしたい方におすすめの一冊だと思います。
資格と勉強も必要でも好きなことで遊びたい(遊びの経験は人生の投資と思う)
一番は楽しく遊びたいのが一番ですね。建設業では家族もっている人もいますし、友達も当然いる方もいます。しかし問題は・・・
遊ぶ時間が合わないということが多々あります。
私もそうでした。夜勤とか日勤でも残業でクタクタ・・・
本当にやりたかったこと・・・たくさんあります。
あとから後悔:やっておいた方がよかった事その1
現場やってるから大丈夫とか勝手な思いで、飲み食いして気づいたらお腹ポッコリして、正直おじさんになってしまった。
あとから後悔:やっておいた方がよかった事その2
現場やってると現場に夢中になって家庭と向き合わない・時間が取れない現場も都合よく合わせてくれない。
あそこに行きたいと思うなら早めにいくのがおススメですね
あとから後悔:やっておいた方がよかった事その3
一番は彼女も作るのも大変だし携帯で探してみるのも今の時代にあっているのでおススメですね。
あとから後悔:やっておいた方がよかった事その4
職人さんでも改造して人とかもいますし、現場監督でアウトドアが好きって人には車は一番興味があると思います。
私も見栄えだけの為に安い外車・・もう10年近く乗ってる・・・
資格取得して給与あげて生活レベルをアップしましょう
現場で働いてる以上は、いつも我慢。
他にもいいものを食べて、普段はいい服を着て少しでも楽に生活したいのが本音ですよね。少し余談でしたが資格取得と趣味も大切に
まとめ
今回は危険物取扱者の資格について解説していきました。
意外と危険物取扱者の資格って種類が多く、それぞれ出題される問題や取り扱うことができる危険物が限られているということが分かったかと思います。
再建では、企業によっては危険物取扱者を設置する義務を課しているところもあるので転職する際にとても有利に働く資格ではないかと思います。
これを機会に危険物取扱者の資格にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。