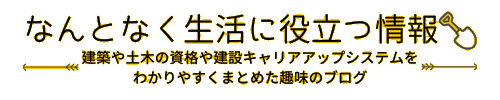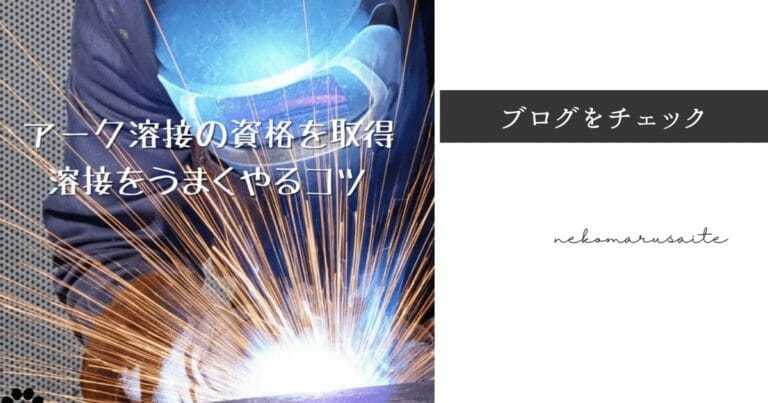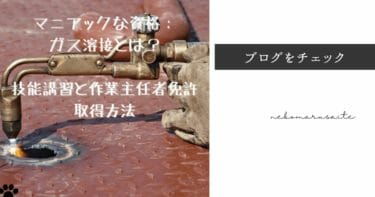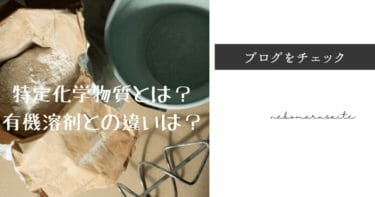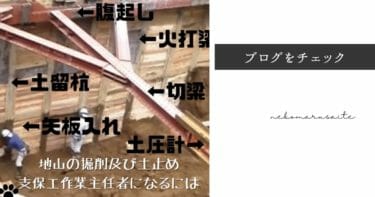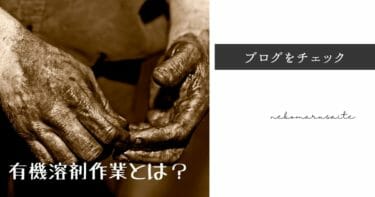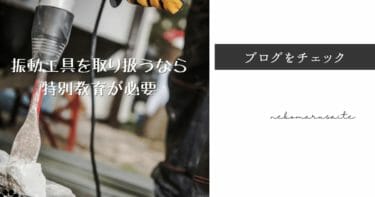この記事では、アーク溶接を使用する際の資格を取得する方法と、アーク溶接のやり方などを解説していきたいと思います。
アーク溶接って他の溶接と何が違うのだろう?と、このように「溶接」という言葉は皆さん聞いたことがあるので、鉄板や金属を溶かしてくっつける作業というのは分かるかと思います。
ですが、アーク溶接の「アーク」って一体何なのかなど、溶接といっても何が特長なのかよく分からないですよね。
溶接はアーク溶接が一般的ですが、その危険性を知らないと大事故になる可能性があります。
そのため、特別教育を受講して教育を受ける必要性があります。
そこで、今回はアーク溶接の資格について、またアーク溶接のメリットやデメリットを含めて解説していきたいと思います。
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。
建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました
以前紹介したガス溶接については、こちらから読むことができます。
この記事では、ガス溶接の資格取得方法とその作業主任者になるための資格を取得する方法について解説していきたいと思います。ガス溶接作業にあまり馴染みがない方にとっては、どんな資格がいるのか、またその作業内容についても良く分からないかと[…]
このブログは他にもこのようなことがまとめてあります。合わせて気になる記事を確認してみてください。全体を確認するにはこちら
2021年アーク溶接の法律が変わった溶接ヒューム
令和3年4月1日から施行になった内容です厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
溶接ヒュームとは、
アーク溶接時に発生する溶接ヒューム(以下,ヒュームという)は,アークの熱によって溶かされた金属が蒸気となり,その蒸気が空気中で冷却され固体状(金属酸化物)の細かい粒子となったもの
を指します。 つまり溶接に金属がとけた時に昇る煙のことになりますね
アーク溶接を屋内作業場で行う場合は以下の点がポイントして注意しなければならなくなります。
- これまでと同等かそれ以上の換気の実施。
- ヒューム濃度の測定をする。
- 作業場の床の水洗掃除を毎日1回以上行う。
- 特定化学物質作業主任者を選任する。
- 特殊健康診断の実施。
溶接ヒュームの新たな規定と変更の内容とは
このポイントとしては、
- 溶接ヒューム及び溶接ヒュームを含有する製剤その他のもの
- 溶接ヒュームの含有量が
- 重量の1%以上
- 金属アーク溶接等作業に係る「ばく露防止措置等」が設けられる
といった内容が定められています。
つまり、溶接ヒュームも特定化学物質に指定されているので扱う時は十分注意しましょうといった内容が設けられているということです。
この記事では、特定化学物質を扱う際の資格と資格講習の内容について解説していきます。また、間違えやすい「特定化学物質」と「有機溶剤」の違いについてもあわせて解説していきます。特定化学物質を扱うときは、特化物講習と言われる資格[…]
アーク溶接特別教育を取得する前に知っておきたいこと

アーク溶接は簡単にいうと、電気の力で金属物の間間にスパークさして火花を発生させる、これを「アーク」といいます。
ここで発生する熱を利用して金属の溶接棒で金属同士をくっつける作業を「アーク溶接」といいます。
こうしたアーク溶接の作業はこのような危険性を伴います。
アークが発生する時火花と光がまばゆい光で目がチカチカします保護具を使わずに溶接を繰り返すと夜中に目が熱くなり、涙が止まらなくなります。
すごく目が痛くなり目を薬とか職人さんはいますが、実際この光を防ぐ遮光レンズ付きの保護具を適正に使わないと後ですごく後悔します。
また電気の力を利用して行うため、雨等で屋外で溶接する場合には感電等の恐れがあり、金属を溶かすため火傷の恐れもあります。
そうした危険性を伴うので、より安全な作業を心がけるためにも資格は必要なのです。
溶接作業簡単なのか?難しいのか? コツとは?

作業自体は簡単そうに見えますが、溶接のコツが必要で金属同士をくっつけた際に隙間がないようにしなければならないです。
薄い鉄板では鉄板同士が溶けてしまってうまくつかない場合や溶接した部材にものを乗せたときに溶接が切れて落ちることもあります。
手の動きを数字の8の文字を書くように溶接棒のついたフォルダーを動かしていくのがポイントです。
ただ、縦方向に溶接する場合や横方向に溶接する場合によって若干手の動かし方は変わりますが、金属同士を動かないようにまず仮止溶接して、呼吸を止めてフォルダーを動かしていくとうまくいきます。
また、溶けた溶接カスが付いているのでそれをきれいに叩いて取ると溶接がうまくついているかどうか確認ができます。
この方法はあくまで建設業で使う山留支保工などで厚い鉄板を溶接する場合にやっていた内容です。
山留支保工について詳しくは、下の記事から参考にしてみてください。
この記事では、「地山の掘削及び支保工作業主任者」とは、どういった資格なのか、その作業内容と資格を取得する方法について解説していきたいと思います。地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習とはどういう資格なんだろう?と、このように[…]
アーク溶接作業者なら知っておきたい工具
アーク溶接を使う作業者は、特に必須なのは遮光面を用いて作業をすることが多いです。

オーソドックスな遮光面ですが、必ず溶接の際には必須のアイテムになります。
溶接する際には溶接棒も箱のまま持ち歩くと以外と重たいので専用の腰袋につけれる袋があると便利ですよね。
溶接は火災事故が多い:危ない作業
ALC金属加工等の業種でもアーク溶接は用いられ、製造業や車等の製造でも用いられています。
アーク溶接の特別教育は、作業に伴う溶接機械の不備や管理の不足・作業者の作業方法や感電火災・火傷など重大な災害があります。
溶接中の火花が飛び散り建築資材に燃え移り火災になったケースもあります。
このようなケースが多いため、労働安全衛生法の中の労働安全衛生規則の中では事業者はアーク溶接機を用いて行う金属の溶接に関して特別教育を実施しないとならないと定められています。
このような労災事故もあるのでアーク溶接の事例
長野・松本労働基準監督署は、ベトナム人技能実習生2人に防じんマスクなどの呼吸用保護具を使用させなかったとして、足場など仮設資材の修繕・整備を営む㈲飯田整備工業(長野県飯田市)と同社取締役を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで長野地検松本支部に書類送検した。
技能実習生らはいずれも20代後半の男性で、長野県安曇野市にある同社松本整備工場で半自動アーク溶接機を用いた足場材などの補修作業に従事していた。金属をアーク溶接する際には、ヒューム(加熱により発生する粒子状物質)などの粉じんが発生する。粉じんを吸い続けるとじん肺などになる恐れがあることから呼吸保護具を使用させなければならないが、同社は令和2年8月1日~9月15日までの約1カ月半、これを怠っていた疑い。
同労基署は、「作業現場にはほかにも何人か作業員がいたが、アーク溶接を行っていたのは技能実習生2人だけだった」としている。
【令和2年11月24日送検】
このような事故を通して考えていくとアーク溶接は危険な作業であることは変わりないので絶対に注意しないといけません。
ただ、ガス溶接と違ってアーク溶接はあくまで特別教育なので国家資格ではありません。
ちなみに、ガス溶接と合わせて取得すると仕事の幅はさらに広がります。
アーク溶接の取得する講習内容とは?そのカリキュラムはどのようなものなのか?次のページでまとめていますので合わせてチェックしてみてください。
- 1
- 2