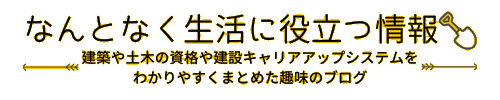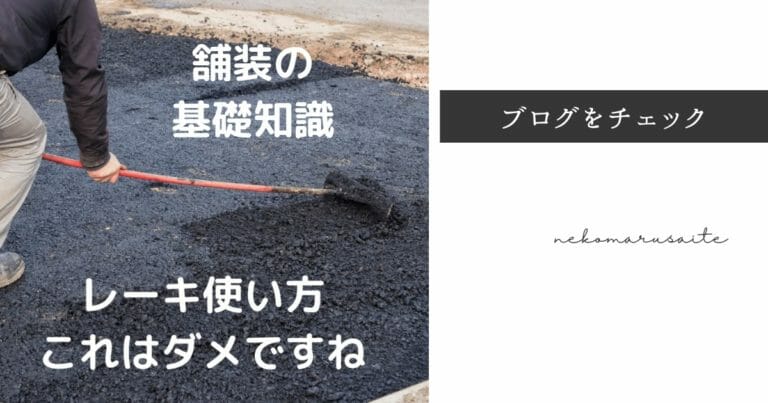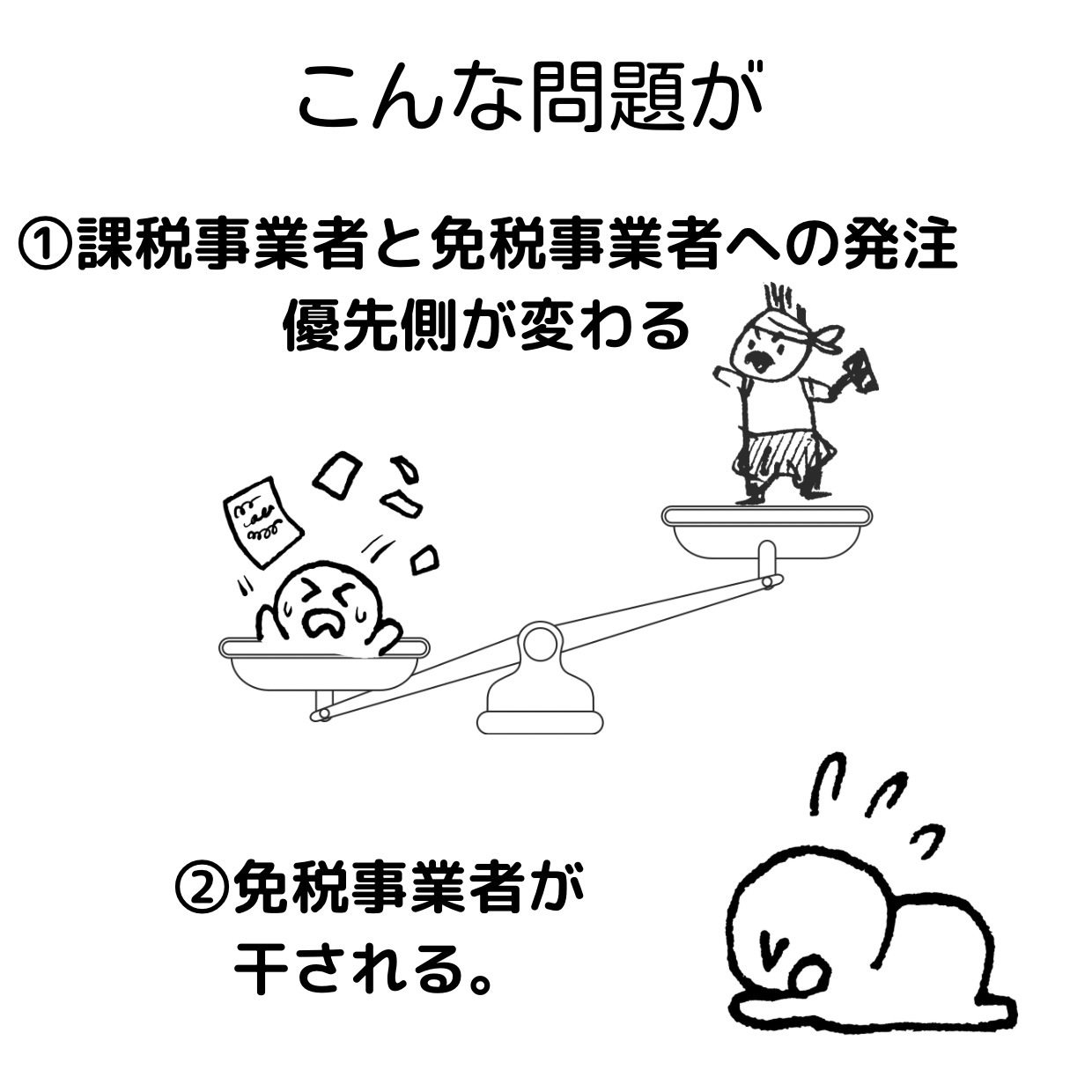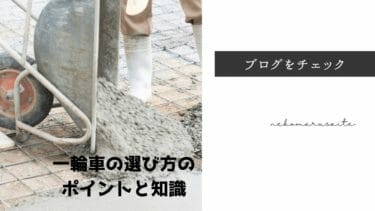この記事では、道路舗装工事の施工方法と施工する際に気を付けたいポイントを現役現場監督の筆者が解説していきたいと思います。
皆さんは普段何気なく使用している道路がどのように作られているのか知っていますか?
実は、道路舗装の工事は、土木では難易度が高い仕事です。
そうした舗装工事を知ることは土木屋さんでも重要なところですね。
そこで、今回は舗装工事の方法と施工をする際に気を付けておきたいポイントを解説していきます。
舗装工事にはうまく施工できる方法がある?現役現場監督がまとる 舗装工事 注意点 と合材種類と管理方法 | なんとなく生活に役立つ情報 (nekomaru.site)
このブログを見て連絡してきた、練馬の新人保険屋さんの千尋(ちひろ)さん。と言う方がいらっしゃいまして建設業の実態教えて欲しいと言われてブログを一緒にやることになりました。
舗装工事に知っておくべき知識と手順
まずは知識を積むということですが、アスファルト工事では、是非取得しておきたい資格として挙げられる資格はいくつかあります。
取得しておきたい資格 土木施工管理技士・舗装工事管理技術者
土木施工管理技士とは、土木に関わる施工の品質管理を担う国家資格です。
舗装施工管理技術者は舗装に特化した資格で5年更新の資格になります。民間資格試験ですが難しい専門性があり道路会社とかは知識を求められる中で取得はおすすめですが、やはり更新があるのがネックになります。
国家資格の土木施工管理技士をオススメします!
参考として舗装施工管理の申し込み先はこちらから内容をチェックしてみてください。
1級舗装施工管理技術者合格に向けて過去問10年分ダウンロードして対策・傾向に過去問題攻略
2級舗装施工管理技術者過去問・問題集10年分ダウンロードで合格への道
さて、取得したい土木施工管理技士の資格は1級・2級とそれぞれあり、それぞれ管理する工事の規模・試験内容が大きく違います。
道路工事における主任技術者や大規模な道路工事の監理技術者として現場管理を担うことができる上、資格を取得している技能者が少ないことから、とても需要のある資格でもあります。
是非、土木工事のスペシャリストとして業務を遂行するのであれば、取得しておくことをおすすめします。
以下の記事では、土木施工管理技士の資格を取得する方法を解説しているので合わせてチェックしてみてください。
舗装工事で技術がいるのは?レーキ と プレート操作
レーキという道具は知っていますでしょうか?舗装工事ではレーキとプレートの扱い方で施工の技量が見えてきます。
舗装材は合材とか言われて、機械で施工もしますが細かい不陸調整の敷き均しはこのレーキ(トンボ)使用して敷き均します。端っこなど大きな機械で転圧出来ない箇所はプレートで細かく転圧していきます。その為、この2つの手順を扱ってる人が実は舗装で一番技量を持っているということですね
舗装工事 注意点① 舗装レーキ技術

レーキの引き方
- 合材をたくさん、刃先で押して敷き均ししようとする人(写真のような感じ)これはダメです。
- あくまで不陸敷き均しをするのがレーキで、舗装の砕石(粒)を転圧したときに引っかかる大きいモノを除去
- 一度、施工している舗装の敷き均し状況を目でみて全体の敷き均し厚さをみて
- レーキを押すのではなくて引いていく、最後に少し跳ね上げるようにすると砕石の大きな粒を跳ねる
- そこに細かい砕石レーキで引いて敷き均しをする
その際に、レーキにはアスファルトがまとわり付くので油(軽油)をブラシで塗りつけ、カワスキでレーキの刃先についた合材を都度取りながら施工するといいですね。
舗装工事 注意点② 舗装 プレート やり方

舗装工事で次に大事なが、舗装プレートのかけ方
プレート稼働時はジョーロで水をまきながら施工します。私が仕事はじめたときは軽油をまいてました。油でプレートに合材がくっつかないからですね。それから薄ベニヤを600×600ぐらの四角で切って敷いて、そのうえからプレート叩いてました。
今は、常時油を使うことがアスファルト自体の分離を促進してしまうのではないかということで、水で転圧しますが、転圧の際にあまり機械に自分の体重をかけない、かけると轍が出来るので、継ぎ目の出ないように舗装が冷めないように手早く舗装転圧していきます。 轍が出る場合はおおきなベニヤで均等に転圧していきます
では、大型の道路などでの舗装の手順を説明していきたいと思います。